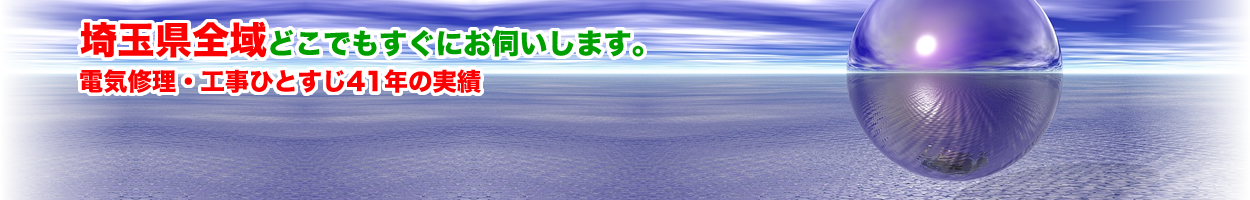◆埼玉県の飛龍太鼓です。
◆和太鼓演奏でイベント、式典を盛り上げます
◆30年の実績が有りますので、あらゆる会場での
演奏経験が、ございます。
◆イベント幹事様と、じっくり打ち合わせを致します
◆演奏規模―――会場20000名から、100名迄、お気軽にご相談ください。
◆屋外会場ーーマラソン大会応援、お祭り会場、ショッピングモールアトラクション、地域商店街客寄せ、展示会場アトラクション等々
◆
◆打ち合わせ電話
090-1770-4991-飛龍源一郎迄
◆詳しい内容http://hakuryoku.jp/
◆太鼓の豆知識
鼓
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「
つづみ」はこの項目へ
転送されています。漢字の部首については「
鼓部」をご覧ください。
(つづみ)は
日本特有の伝統的な
楽器のひとつで、もっとも狭義には小鼓を指す。
砂時計型、または木製、ドラム缶型の胴の両面に
革を張ってこれを
緒で強く張る。緒は、
能楽の世界では
調緒(しらべお)または「調べ」という。この緒を締めたり緩めたりすることで音色を調節しながら、一方もしくは両方の革を手または
桴で打って演奏する。その形態によって小鼓、大鼓、
太鼓、
羯鼓などがある。発音については、古代
インドの
打楽器 dudubhi または dundubhi から出たという説と、
中国の都曇鼓(つどんこ)の音から出たという説がある。
起源[
編集]
鼓はインドで発生し、その後、中国で腰鼓(ようこ)、一鼓(壱鼓)(いつこ)、二鼓、三鼓(三ノ鼓)(さんのつづみ)、四鼓、
杖鼓(じようこ)等と多数の種類が発生した。これらは総じて細腰鼓(さいようこ)と呼ばれる。腰鼓は腰に下げる細腰鼓で、日本には
7世紀初めに伝わり、呉鼓(くれのつづみ)として
伎楽に用いられた。一鼓、二鼓、三鼓、四鼓は
奈良時代の日本に、
唐楽(とうがく)用として伝わった。後に腰鼓、二鼓、四鼓は絶えたが、壱鼓は
舞楽に残り、三ノ鼓は
高麗楽(こまがく)で使われている。また中国から日本に伝わった民間芸能である
散楽(さんがく)にも鼓が使われており、
正倉院蔵の「弾弓散楽図」には、鼓を桴や手で打つ様子が描かれている。こうしたさまざまな鼓が中国から伝来し、やがて小鼓、大鼓(おおつづみ)が日本で成立した。
杖(桴)を使って演奏する杖鼓は、両面の革に異種の材を用いるのが特徴で、胴端の径と革面径ともに大小がある。後に
朝鮮半島に伝わってからは大型となった。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
アオキ総合サービス
http://www.aokiservice.com/
住所:〒347-0117 埼玉県加須市西ノ谷42-1
TEL:0120-029-028
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇